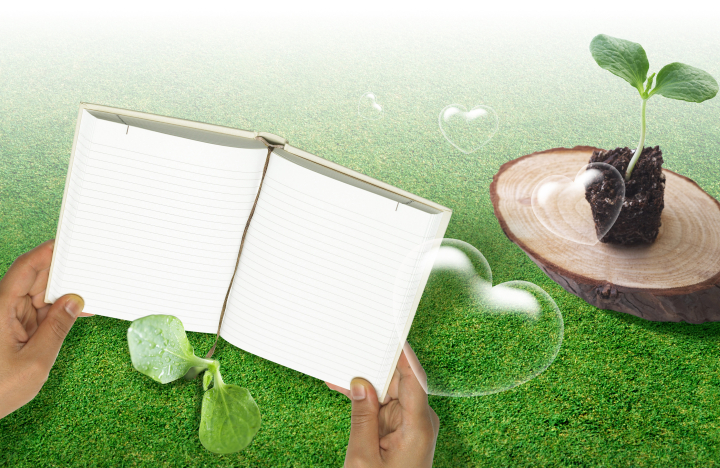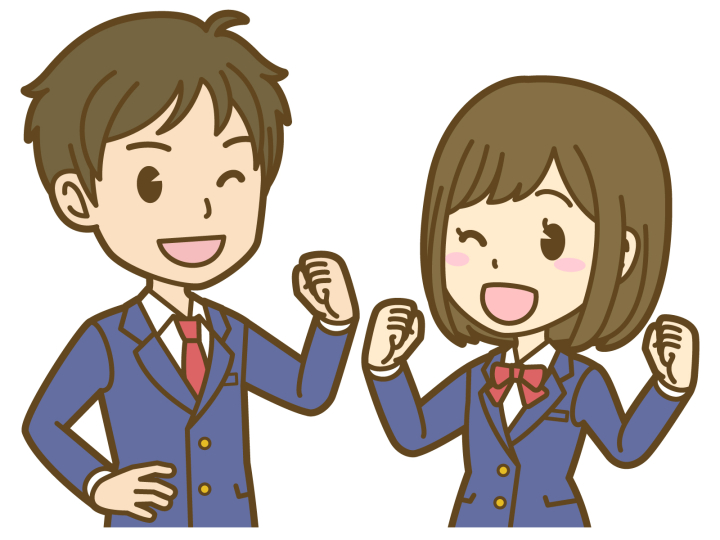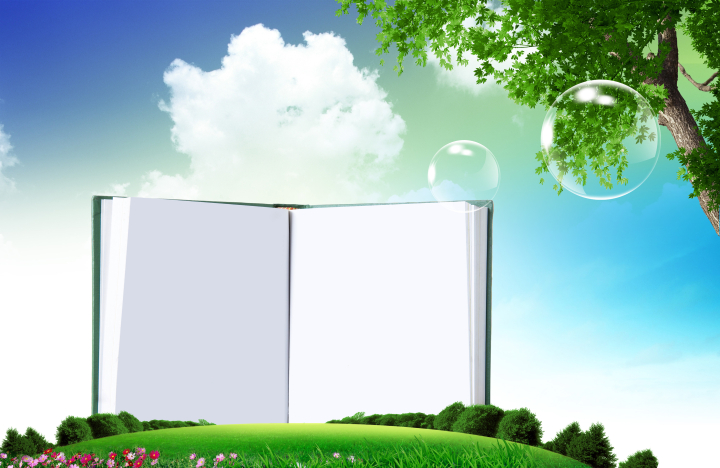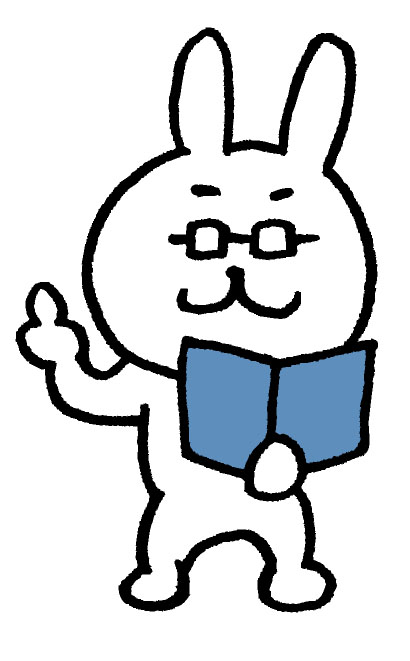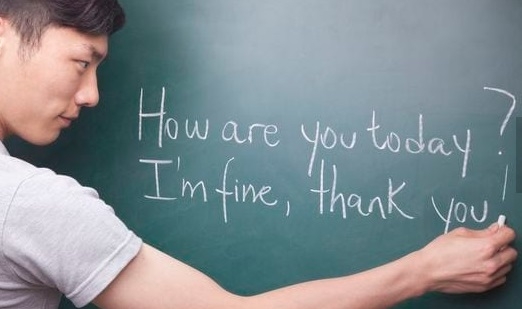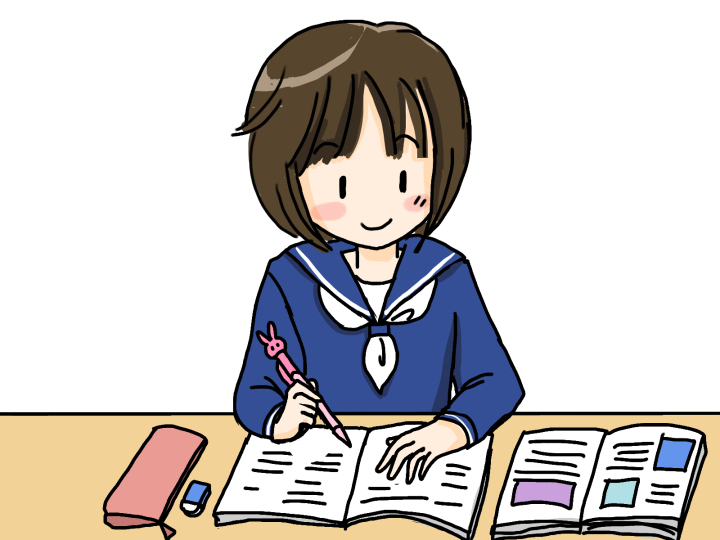Q1.夏休み前の進路相談で「内申が足りないのでその高校の受験は無理」と学校から言われました。そうなんですか?
A1。学校はできるだけ余裕を持たせて受験させたいと考えますので、一般的に言われている合格基準内申より2つ以上余分に持っている生徒のみの受験を許す感じです。ただ、今は確かに受験内申には足らないが、これからどうやって頑張れば受けることができるようになるか、どうやって上げていけばいいのかを、生徒といっしょになって考えてあげるというのが、本来の進路指導です。「無理」という言葉は進路指導では親や生徒には決して言うべきではないでしょう。今のままで充分受かるような高校だけを進めるようなそんな進路指導なら誰だってできますよね。
Q2.うちの子どもは「私立単願」を勧められましたが、これってどんなものなんですか?
A2.愛知県は公立高校が2つ受験でき、かつ併願として私立高校も受けれるという特異な県です。その大きな権利を捨てさせ、ある一つの私立高校だけを受けさせるという制度です。もちろんだから必ず合格はできますが、もったいない限りです。内申に1がなければまず断ったほうがいいでしょう。愛知県の私立なら、併願でほとんどどこでも受かります。あえて単願にする理由はありません。ただ、単願に決めてしまうとその生徒にはそれ以上何もしなくていいので、学校は楽なんでしょうね。
Q3.民間の模擬試験は受ける必要があるのでしょうか?
A3.受けても良いと思いますが、注意することが3点あります。
1点目はその試験が、愛知・岐阜・三重3県共通などではなく、愛知専用の模試であること。
2つ目は、たとえ愛知専用であっても、データは尾張の高校中心で、三河の高校に関してはあまりしっかりしたデータが揃ってないことが多いこと。
3つ目は、その会社が出す志望校別の合格率はかなり甘めに作られていて、学校の進路査定の時に「合格率がこれだけあると模試のデータを持ち出しても、あまり信用されないこと・・・・などです。費用も1回3000円~4000円位すると思います。
また、中3生ならいいのですが、中1や中2生に模試は不要です。実力を知りたいなら学校の実力テストで充分ですよ。
Q4.うちの子はゲームばっかりやって勉強しないのですが、親としてどうすればいいでしょうか?
A4.中学生のゲームを中心としたスマホの依存性が勉強の大きな妨げになってから随分経っていますが、その影響はますます拡大している感じですね。親としての対策の一つは、子供の前で親が決してスマホを使わないということです。テレビを見ながら、食事の最中や、子どもと話をしている時などで、親が子供の前で平気でスマホを使っているのを見せたりすると、もう子どものスマホの使いすぎを注意しても、子どもは反発するだけです。内容や緊急性など子どもの理屈にはありません。親が子どもよりもスマホ第一にしているとして、子どももスマホから離れなくなっていきます。スマホが鳴ったらすぐ別の部屋に行きましょう。そしてすぐ戻ってきましょう。子供の前でスマホを取って話したり、メールやラインを打ったりするのをやめることからまず始めてみてください。
Q5.そもそも中学の勉強って将来役に立つの?
A5.中学の勉強がそのまま役に立つほど、世間は甘くありません。中学の勉強レベルなんで「世の中に役に立つ」レベルではありません。ただ、その後、高校や大学でより高度な勉強に入っていくのに必要なのです。高度な学力・知識があって初めて「人のためになる仕事」ができるのです。
よく「成績が悪くたって、私のことだから、別にいいじゃん。放っといてよ。」と言う生徒がいますが、勉強は決してあなたのために勧めているのではなく、社会を良くするために勧めているということを知ってほしいとも思います。あなたにもその役を担ってほしいから勧めているのです。
どうです?みんなのためと考えれば、勉強って決して辛くないでしょう?
Q6.数学ってどうやって勉強すればいいのですか?
A6.中学レベルの数学は、ほぼ暗記力が勝負です。数学は思考力の科目と言われていますが、それは大学レベルの話で、中学・高校まではほぼ暗記力の科目です。数学の先生も最初は暗記から入ったはずです。数学のできる者はすべてより多くの問題と解答を覚えているだけと言えるのです。私も30年近く数学を教えてきましたが、問題を見たら「ああ、あの手の問題か」とその方法がすぐでてくるだけで、決して思考力があるとは思っていません。応用問題にしても同様で、ただ多くの問題を覚えているだけです。
ということで、数学の勉強方法は、できなかった問題や間違えた問題の解答方法を覚えることに専念してください。同じ問題を覚えるまで繰り返し解いて見てください。そして基礎、応用含めてできるだけ多くの問題を暗記していってください。
その際、計算はできるだけ大きな紙に、できるだけ大きく書いて行うことがコツです。
Q7。塾の自習室って行かせていいのですか?
A.いいとも思います。家の、特に自分の部屋で勉強するのが何故か一番勉強がはかどらないという生徒が多いので、外で勉強することは良いと思います。ただ、友達が近くに居ますので、かえって遊んでしまう、とか、行き帰りに無駄な時間を使ってしまう危険性はあります。また、自習室を管理する先生がその部屋の中にいつもいないと、生徒同時が喋ったり、遊んだりできて、逆にマイナスです。生徒同士で一言も話させない「私語厳禁教室」レベルでないと意味がありませんので、その点を調べておいてください。「塾に勉強しに行っているから大丈夫」と安易に考えるのは、少し危ないかも。
Q8。内申はどうしたらあがるのですか?・・・その1
A.まずは内申の観点別評価「関心・意欲・態度」でAを取らなければ、どれだけテストの点数が良くても、5は取れません。つまり学校ではこの観点を一番重要視しているのです。しかし、逆に言うと、この観点の対策をしっかり取れば、テストの点数以上の効果があるのですから、頑張り甲斐がありますよね。
私も小学、中学、高校の教員免許を持っていますので、その辺は得意分野です。極めて簡単で、最大の効果が出る方法をこっそり教えて差し上げます。一言で言うと、
「授業中、いつも顔を上げて、先生の方を見ている」ことです。説明中に決して下を見てはだめです。正直言って、先生の話は聞いていなくても構いません。ただ顔を先生の方に向け続けていればいいのです。実は説明を聞くつもりはなくても、先生の方をいつも向いていれば何故か自然と話が耳に入ってくるので、一石二鳥なのです。
つまり顔を上げているだけで、「関心・意欲・態度」と成績が同時に上昇するのです。よって、内申がアップします。先生の説明を、メモを取りながら聞くのは一番駄目な勉強方法です。聞き逃しも多く、下を向く度に印象も悪くなります。成績の良い生徒をよく見てみてください。いつも顔を上げていませんか。先生だって、見つめられるのは嬉しいんですよ。きっと。
Q9.英会話教室って効果あるのでしょうか?
A9.充分あると思います。特にリスニング力には効果的ですね。私も、アメリカに10年近く住んでいる教え子を呼び寄せ、ベネッセ英会話教室を開いて、10年近くやらせたことがありますので、よくわかります。年少から来させたりして楽しそうでしたが・・・・
ただ、英会話教室だけでは、入試的な英語総合力はあまり期待できませんでした。英会話とは別に、文章読解力や文法構成力などをしっかり養う必要がありますね。中学英語を、「英語に慣れる」的にマスターさせていく方法は時間とお金がかかり過ぎて、かなり無駄な気がしました。ので、私の塾では早々に英会話教室はやめましたが・・・
定期テストや実力テストや入試のリスニングの配点はそれほど大きくないので、長文読解力の方に力を入れた方が総合点を上げやすいのは確かですね。
Q10.国語の入試問題などで出てくる「4択問題」を解くコツってありますか?
A10。4つのうち、確実に間違いなのがまず2つあるはずです。まずはその2つをカットすることです。そして、入試問題くらいのレベルになりますと、残りの2つが2つとも正解という場合があります。このような選択肢の作り方が入試問題の特徴で、紛らわしいこと限りなしです。では、どうすれば正解にたどり着くかと言えば、2つとも正解の中、より正解の方、いわゆる◯を選ぶというよりも、◎の方を選ぶ必要があるのです。◎こそが正解なのです。これが4択にしてある理由なので、今後注意すれば、おそらく入試の国語の点数は上がりますよ。
Q11。夏休み中に注意しなければならないことはありますか?
A11.クーラーが学校に設置されるようになったら、夏休みは不要だと思うのですが、今更変えることはできないようですね。正直言ってこの40日間で、ほとんどの生徒の学力はガタ落ちです。普段なら学校で最低でも6時間ほど勉強していたのが、生徒によっては1日ゼロ時間もありえます。それが40日間続くのですから、その影響力は計り知れません。それを毎年続けているわけですから、何と勿体ない話ですよね。
クーラーがあるのだから、毎日学校に来させてきちんと勉強させれば、日本の学生の学力は大いに伸びていけると思うのですが・・・多くの中学校で渡される「解答付き問題集」の宿題なんて効果はゼロです。こんな状態が毎年繰り返されているのです。
しかし、これは、実は、最大のチャンスでもあります。つまりほとんどのライバルが夏休み中は足踏み状態か、または逆行しているワケですから、抜こうとしている者にとっては好都合なのです。本当に頭の良い、成績の良い生徒たちはこの機会を決して見逃しません。あなたはどうでしょうか?一般の生徒同様、だらけた夏休みを過ごしていませんか。そうすれば9月になるともうライバルに追いつけなくなりますよ。
夏休みに注意しなければならないこと・・・おわかりになりましたよね。
Q12.テスト週間に親が注意することは何でしょうか?
A12.2つあります。1つ目は、テスト週間は決して子どもに「勉強しろ」と言わないこと。親から言われて一番ムカつく言葉は「勉強しろ」です。これはあなたの子供時代を思い返しても同感できますよね。もちろん私もそうでした。特に母親から言われる「勉強しろ」ほどやる気をなくさせるものはありませんでした。でも誰しもそんなことは忘れて、親になると今度は子どもに「勉強しろ」を連呼してしまうのです。しかもテスト週間には特に多く。まず、これは必ずやめてください。注意したければ、塾の先生に頼んでください。他人の冷静な注意なら、子どもは反発しません。肉親は一番駄目ですよ。
2つ目は、テスト週間だけでも、スマホを取り上げてください。これも親ができなければ、塾の先生に頼んでください。塾の先生に頼まれたからと言えば、まず大丈夫でしょう。「文句は塾の先生に言って」とでも言っておいてください。しかし、使用禁止はテスト週間だけです。それ以外はおそらく無理でしょう。ただ、テスト週間だけはスマホを使わないという習慣は、今後大きな力となるはずです。是非頑張ってください。子どもに頑張らせるには、大人もそれなりに頑張る必要があるのです。
Q13。理科が苦手で困っています。どうすればよいでしょうか?
A13. 理科ほど「分野」によって内容が異なる科目はありません。中学理科は、物理・科学・生物・地学の4分野によっても、また同じ分野であっても、それぞれの内容が細かく独立しているという特徴があります。つまり英語などのように、中1の基礎がわからなければ中2の内容もわからないなどということはないのです。
よって、一つ一つを徹底的にマスターすることに徹するのがコツです。今日は「光合成」、明日は「地震の計算問題」、明後日は「気体の性質」、その次の日は「光の反射」・・・などのように、細かく一つ一つをクリアしていく感じで勉強すると良いでしょう。
私も30年近く理科を教えていますが、それでも分野によって、得意、不得意があります。生徒にもあって当然です。だから決して諦めず、1つ1つ攻略して行ってください。できる、わかる分野を少しずつ増やしていきましょう。
Q14。「公文」って、中学の数学で役に立ちますか?
A14.役に立つと思います。実際、中学の数学は、たとえ図形であっても、最終的には「計算」が必要となってきます。 計算力が無いと中学数学は点が取れないのです。その理由で公文はとても良いと思います。
計算力を付けるには、数をこなさなければなりません。小数、分数、そして特に割り算は、高校数学でも必須です。一時期、「大学生のくせに分数計算ができない」と、嘆いていた大学教授も居ましたが、数学を教えている者にとっては、生徒の計算力は必須なのです。
時間とお金に余裕があるならば、小学生の時だけで構いませんので、公文に行かせるのもいいでしょう。計算力で引っかからないならば、思考力もグングン伸びていきます。私は数学を教えている時が一番楽しいのですが、計算間違いだけで解答にたどり着けない生徒を見ている時ほど、辛いことはありません。
Q15.うちの子は集中力が無くて困っています。何は良い方法はありますか?
A15.保護者の方から一番多く聞かれる質問ですね。俗に言う「うちの子はやる気になればできるのですが・・・」の、「やる気」が集中力のことを言っているのでしょう。
「頭の良い子は集中力がある子」とも言われるように、集中力は成績アップには必須なのです。この訓練をしない手はありません。訓練次第でこの集中力はグングン伸びるので、是非頑張ってみてください。
方法は極めて簡単で、寝ている時以外は、いつ、どこでも、誰でも、そして人前で堂々とできるスグレモノです。お金もかからず、効果は早い人なら1週間で出てきます。
それは・・・・その場で「耳を澄ます」ということです。何かを見ながらでも、人の話を聞きながらでも構いません。耳を澄まして、耳に集中して、遠くの音を聞き取るように耳をすますのです。例えば、1キロ先の駅の様子を聞き取るような感じで。
脳に一番近い感覚器官は、耳と言われています。禅の坊さんが何時間でも坐禅が組めるのは、遠い林の中にある木の葉っぱが落ちる音を聞き取るべく、じっと耳を済まし続けているからだと言われています。ただひたすら何時間でも葉の落ちる音を待ち続けているだけなのです。
勉強が長続きしない。すぐ飽きてしまう。どうもやる気が出ない・・・などの時はすぐ10分くらい、耳を澄ましてみてください。その時、目を閉じるとなお効果的です。より耳に集中できます。慣れてくると、脳が動き出すのが感じられるようになります。それに、深くて長い呼吸が加わればもう完璧です。10分もすれば、みなぎるような集中力が湧き出てくるはずです。ゲームをしている時と同じくらいの集中力も夢では無いですよ。「集中力がいつでも復活させうる」なら将来これほど役に立つ才能はまず無いでしょう。是非頑張ってみてください。お勧めです。
 遠く波の音を聞く感じでもいいですよ。
遠く波の音を聞く感じでもいいですよ。
Q16.学生アルバイトが教える塾って、どうなんでしょうか?
A16.学生アルバイトであっても、熱心に教えてくれる先生は多く居ます。学生だから、アルバイトだからと言って、下に考えるのは良くないと思います。
私見ですが、学校の先生になりたいと思っている人には、学生時代に一斉授業の塾で少し授業の練習をすることをおすすめ致します。学校の先生になった後は、先輩先生からの授業のアドバイスは全く無いので、慣れない授業の影響は即、生徒に来てしまうからです。
できれば、塾のバイトで鍛え上げられて、できるだけうまくなって学校に来てほしかったなあと感じるような不慣れな若い先生たちをよく見ます。学校と違って塾は、塾長が学生バイトを鍛え上げますし、上達しなければクビにもできます。親からの注文も学校の比ではありません。たくましい先生に育つ要素は学校よりも多いのです。
そういった意味でも、塾で頑張っている学生アルバイトには是非「頑張れ!」という気持ちで見守ってあげてほしいと思います。それが、私のいる塾という世界の一つの役割のような気もします。(ただし、マンツーマン授業を学生アルバイトに教えさせるのはさすがに負担が大きすぎる感じはしますが・・・)
 先生、さよなら。
先生、さよなら。
Q16.公立をダブル落ちしたら、どうなるんですか?
A16. 現在、公立入試テストは1回受けるだけで、その点数が、志望校2つの合否判定に使われます。だからその1回の入試テストを大きく失敗すると、公立ダブル落ちの危険性が今までより増えることになる訳です。そうならないように、第2希望の高校を大きくレベルを下げて受験させる傾向にあります。それでもダブル落ちした場合は、滑り落ちとして事前に受けていた私立高校に行くことになるのですが・・・・
ダブル落ちは子どもにとって大きなショックです。今後の自信喪失の原因にもなります。親としては対処に困るところですよね。当塾でも、5年に1件位ダブル落ちの生徒が出ます。そんな時、私はよくこんなことを言っています。
「今度行く私立の高校では、絶対にお前は学年一桁の成績が取れると思う。これだけ公立目指して勉強してきたお前に叶うやつなんているはず無い。しかもお前には、なんの理由かわからないが、落ちたという「悔しさ」も持っている。最強じゃないか。本当の勝負は大学入試だ。今の日本で、学歴として使えるのは大学名であって、大学さえ一流なら、高校名は問題にされない。いい大学にはいってみんなを見返してやればいい。」 と。
大事なのは、どんな高校に通うかではなく、どんな高校生活を送るかである。
そう考えると、ダブル落ちなんてちょうど手頃な塀ってところでは無いだろうか。
私の塾では、高校入試でダブル落ちして、大学でも第1志望が落ちたなどという生徒は今のところ一人も居ない。ダブル落ちからでも、人生は学べるのである!
Q17。国語のテストの点数を上げるなにか特別な方法はありませんか?
A17. 文章読解問題が苦手な生徒は多いですね。加えて、文章読解力を本格的に指導する塾や先生もあまり多くはいません。国語と言えば読書だとばかりに、読書をすすめてくる先生がいまだ多いのも事実ですが、読書の習慣だけでテストの文章読解問題の点を上げることは無理です。テストでは文章を読み取る力と同時に、解答を表現する力も必要とされるからです。
そして読書以外には、国語の点数を上げる術を持たない学校や塾が多いのも事実です。実は、国語こそ確実に点数をあげられる科目なのに、本当に勿体ないと思います。以下をお読みの上、是非国語を頑張って下さい。
(4択問題の答え方は、Q10で述べてありますので、そこを参照して下さい)
文章読解力を確実に上げ、国語の点数を伸ばす方法というのは・・・文章読解問題集の ①問題文 ②問題 ③解答 の3つを見比べて行くだけでいいのです、自力で解く必要はありません。見比べるだけで構いません。そして「点の取れる解答の仕方」を掴んでいくのです。読解力を養う必要はありません。要は問題解答力なのです。
国語の定期テスト対策としては、準拠の問題集2冊以上の問題文+問題+解答の3種を見比べていくとよいでしょう。
実力テストや入試対策としては、準拠ではない読解問題集をできるだけ多く見比べていってください。
時間も極めて短時間で済み、そして確実に国語の点数がアップします。国語の攻略に取り組む生徒はほとんど居ないので、大きな差をつけることもできます。
加えて、入試の国語は全員が完全に未知の文章を読まされますので、この解答力が身についていれば、志望校合格確実です。
(「読書」のような、いわゆる問題の付いていないような文章は、楽しみとして読むのは一向に構いませんが・・・
Q18. 子どものテストの点数の見方で何か注意することはありますか?
A18. まずは点数だけを見ないことです。英語が60点で、数学が70点だとすると、「英語、悪いじゃん。今後は英語を頑張らなきゃ。」と言いがちですが、
もし英語の平均点が55点で、数学の平均点が75点だとしたら、英語は平均点差+5点、数学は平均点差-5点となり、悪いのは数学の方で、今後頑張らなければならないのは、数学ですよね。
また、同じようなことが、同一科目についても言えます。第1回の英語の点数が70点で、第2回目の英語の点数が60点だった場合、「英語下がったじゃん。もっと頑張ってよ。」等と言いがちですが、これも、もし第1回目の英語テストの平均点が75点で、第2回目の平均点gが55点のような場合、もうおわかりのように、1回目は平均差-5点に対して、2回目は平均点差+5点なので、2回目の英語は実際はアップしたのです。本来は褒めて上げるべきなんですね。
このように、学力を正確に判断するには、点数よりも「平均点との差」で見比べていく必要があります。そうすれば、どの科目が苦手で、どの科目が上がったかなど極めて正しく把握できるようになります。
できれば、全科目・全テストの平均点との差だけの記録表を作っていくと、本当の学力と頑張り具合が正しく見えてきますので、是非頑張って作りましょう。
Q19. 歴史が得意になるにはどうすればいいですか?・・・その1
A19. 現在中学の歴史の授業は、3年間のうち、2年半という長い期間をかけて教えます。(地理は2年間、公民は半年間) これだけ長いと、覚える端からどんどん忘れていきますので、全体の流れを掴むことは難しくなり、ごちゃごちゃになってしまいがちです。この流れを正しく掴み、かつ忘れないようにするには・・・・
「教科書を古い時代から順番に、何度でも読み返すこと」です。この学習方法は、元来歴史の教師を目指していた私が、30年間歴史を教え続けて得た方法で、効果は大でした。
歴史の教科書は、あまりうまい文章ではありませんが、最大の長所は流れの順に書いてあることです。ただ何回も読み返していくだけで、自然と流れが掴めます。これはあれより古い、新しいが、段々と掴めてくるのです。特に忘れがちな3年生になってから是非おすすめの対策です。
Q20. 歴史が得意になるにはどうすればいいですか?・・・その2
A20. 歴史の対策として、もう一つ効果的な方法をお伝え致します。
前回、流れを掴むには「教科書を読むこと」と申しましたが、それと同時に行っていただきたいことがあります。それは・・・「年号を覚える」ことです。
愛知県の公立入試を20年以上分析してきておりますが、「歴史の古い順に並び替えよ」とか、「同時代の出来事を選べ」などの問題が必ず出題されるのです。遠く離れた時代の並び替えなら、教科書を何度も読む方法で対処できますが、極めて近い時代の並び替えなどは、実に難しいのです。そこで役に立つのは、「年号」です。これなら数字の並び替えだけで歴史の順序がわかります。
例えば、1787年寛政の改革と、1789年フランス革命の並び替えなんて、時代も近いうえに、国が違っていて、全くつながりがないにも関わらず、その順序をテストに出したりするのが愛知県です。年号の数字なくして絶対にと解けません。
年号の覚え方は、「ボカロ」でもいいですが、昔ながらの「語呂合わせ」が面白いと思います。年号語呂合わせの本も出ていますので、是非、年号をどんどん覚えていって下さい。「いちごパンツの信長」1582年本能寺の変などは、傑作だと思います。
Q21. 大手学習塾の一斉授業って、どうなんですか?
A.21 大手学習塾も、一斉授業形態と、個別指導形態がありますが、お尋ねの一斉授業で言うならば、効果はあると思います。私も8年近く大手学習塾の教室長を務めていましたが、独自の入試情報などはとても充実していたと思います。お金に余裕があれば、大手も充分考えていいと思います。
逆に、小規模の一斉授業塾も、お勧めです。私も多くの塾長と付き合いがありますが、みんな個性的で、あまり金銭のことにこだわらず、熱心に指導している感じです。
どのタイプを選ぶかは、ご家庭(ご両親)の塾に対するイメージに依るところが多いように思います。大手は少しかっこいい、小規模は和気あいあいで楽しそうなど・・
もちろん、金銭的に可能ならば、「指導歴40年のマンツーマン指導」が最も効果的で、最も個性的だと、私は思っておりますが・・・
Q22.月謝袋と口座自動引き落しのどちらがいいのですか?
A 塾業界でも最近は口座引き落としが多く行われているようですが、私は40年間、月謝袋を採用しています。
「子供に月謝袋を持たせるのって危ない」
「落としたらどうするの」
「毎月払うのは面倒くさい」
いろいろご批判はあるかと思いますが・・・・
1.「教育費」が普通の光熱費のように毎月知らないうちに「自動で」引き落とされているのってどうなんでしょう。教育費って毎月認識して払わないでよいものなのでしょうか。決して安い金額ではないのに何と無関心な。しかし月謝袋だとどうでしょう。この塾にいくら支払っているのかが毎月自然と認識できますよね。
下らぬ授業に大金をはらってないか、を毎月確認する。これはある意味親の務めだとも考えます。
2.また、塾としても、ご家庭(親)から貴重な月謝をいただいているのだから、毎月感謝の気持ちを伝えるべきと考えます。誰でもお金をいただいたら、ありがとうと言いますよね。それが世の中では当たり前ですが、なぜか教育の現場ではそんなことはしません。塾の先生からでも入金のお礼を言われたこと、ありますか?給料や従業量が口座自動引き落としだからです。自動的に入ってくるので、「感謝」の気持ちがわかないのでしょう。ある意味教育者の思い上がりです。
私は、生徒から月謝袋をもらう時、生徒に直接「ありがとう」を言います。それが言えるチャンスがあるのが月謝袋の良いところです。勿論ご家庭にもお礼のメールを送ります。こうやって、お金をいただいている事を毎月確認し、感謝しています。すべては「月謝袋」のおかげです。
感謝の気持ち無くして教育は成り立ちません。
 お母さん、月謝に見合うだけの指導を受けていますか?
お母さん、月謝に見合うだけの指導を受けていますか?
Q23.。中1の基礎が一番必要な科目は何ですか?
A. 理科や社会や国語や数学は分野が分かれていますので、取り立てて基礎がなくても大丈夫です。その分野に絞って集中的に勉強すれば、いつでもマスターすることは可能です。が、英語だけは1年の分野の基礎力がなければ、それ以降は完全にアウトです。
中1英語といえば、be動詞と一般動詞の違い、三単現、can、現在進行形、過去形の5つが教科書にでてくるわけですが、これらの違いが上手に使いこなせなければ、2年生になって出てくる、未来形、不定詞、SVOO構文、接続詞、助動詞、比較文、受動態などは、やればやるほど混乱する仕組みとなっています。2年生でほとんど破壊され、中3の使役動詞、形式主語、間接疑問文、関係代名詞、仮定法には到底たどり着かない仕組みとなっています。
にもかかわらず、多くの学校や塾では、ベテラン講師が中2,3生を受け持ち、中1は易しいからという理由からか、新人講師が受け持ったりします。10年くらい英語教師をやればわかるかと思いますが、これでは全く逆です。私は40年間、どんなに忙しくても、中1の英語だけは私自身が教えてきました。中1英語の基礎さえしっかりマスターできれば、中2、中3はどちらかと言ったら新人講師でも構わないのです。
この逆転指導に加えて、困ったことに一番大事なはずの中1の教科書が特に最悪なのです。代名詞や疑問詞がランダムに出てきたり、三単現を習う前に不定詞が出てきたり、助動詞を習う前にcanだけ急に出てきたり・・・・わざとわかりにくくしてあるとしか思えないような構成です。この教科書をそのままの順で教えている先生のもとでは本当に中1英語をマスターできるのはほんの数人でしょう。
私は中学英語と高校英語の教員免許を持ち、40年間、英語を教えてきていますが、
最近は特に、英語が苦手という中学生が増えてきているように感じます。
公立、私立の別なく、文系、理系の別なく、就職、進学の別なく、どんな時でも英語が要求される日本で英語が苦手は致命的です。
中2になったら振り返りが難しく、どんどんわからなくなる科目、そして基礎が極めて重要な科目、英語をいかにマスターするかが、今後の成績において、最大の鍵といえるのではないでしょうか。
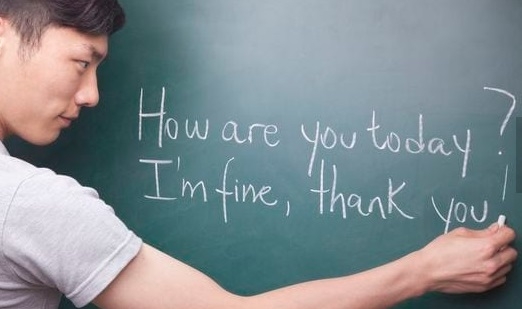 中一英語を制するものが入試を征する!
中一英語を制するものが入試を征する!
Q24. テスト週間中の授業はどうなっているのですか?
A24.テスト週間でもいつも通り授業は行いますが、テスト終了後の授業が勿体ないと判断した場合は、テスト前に、前倒しで授業を行うことも可能です。その時は、土日や祭日を利用しますが、生徒の気持ちがテストに向かっているため、テスト対策としては
効果大です。(日程のやりくりが大変ですが・・・)
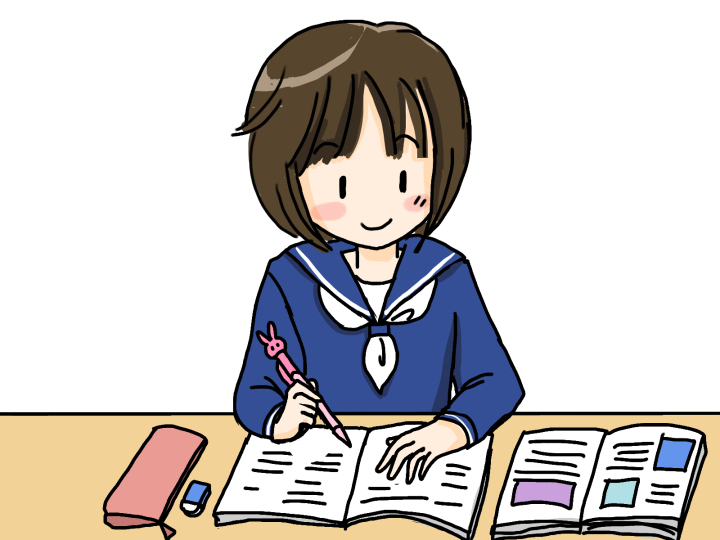 信頼できる塾で思いっきり勉強したい!
信頼できる塾で思いっきり勉強したい!
Q25. テスト週間は課題提出だけで他に何も勉強ができないと悩んでいますが、どうすればいいでしょうか。
A25。課題はできるだけテスト週間前に終わらせておくことが必要です。提出範囲がはっきりわからなくても、90%以上終わらせることは可能です。
元来、テスト週間の課題提出は、日ごろ勉強しない生徒でもテスト週間くらいは勉強させようとする学校の仕掛けなので、課題だけでテスト週間が終わるようでは、決して高得点は取れません。成績の良い子はそんなことは知っているので、課題などはテスト週間の前までに早々と終わらせあり、テスト週間は弱点補強や、難問挑戦を行っています。もうこの段階から差が大きくついているのです。
では、テスト前に課題を終わらせるにはどうすればいいか。それは、日ごろいかに勉強時間を確保できるかに掛かっています。ゲームなどで数時間を使ってしまうような生徒は論外です。もうこの段階で低順位確定です。本当に点数を上げ、順位を上げようとするならば、まず日ごろの勉強時間確保を目指してください。成績、順位の良い生徒は日ごろから頑張っているのです。
高順位な生徒ほどつらい思いをしているものなんですよ。
Q26. 国語の効果的な勉強法ってあるのですか?
A.26. 国語を指導する一斉塾は、ほとんどありませんし、個別指導塾においても、国語指導を要望する生徒はほぼ皆無でしよう。それゆえ、普通の塾には国語を指導できる教師がいませんし、塾の側も国語の先生なんて雇わないのが現状です。
しかも、学校の国語の先生に、国語の勉強法を聞いても、「読書しろ」とか「日記を書け」とかしか言いません。しかし、読書や作文で国語力をあげようとしても、その効果が出るには5年以上かかります。中学生の国語テスト対策としては話になりません。そこで、国語は何も対策しないという生徒が続出するわけです。
しかし、だからこそ、国語に絶対の自信を持てる生徒は強いのです。
国語のテストの出来で学年順位が上がり下がりするような生徒が多い中、確実に順位を上げてくるのです。
では、国語の成績(点数)上げる勉強方法ってあるのだろうか? できれば数か月単位で短期間に・・・・以下、1.漢字 2.初見文章読解問題 の2点で述べてみたいと思います。
1.漢字問題・・・定期テストでは出題される漢字は決められてきますので、それらをすべて覚える必要があるのは言うまでもありませんが、何回も書いて覚えるのは時間の無駄。漢字は「書かずに見て覚える」練習を日々すること。小学生の頃、やたらと書かされた記憶があると思いますが、あれは書くことが重要だった訳ではなく、書いている間じっと見ることとなり、目で覚えさせるためにやらせていたというのが真実です。つまり、これからは目でじっと見て覚える練習をしていけば、早く、大量に覚えることができるようになります。慣れれば今までの10分の1の時間で完璧です。漢字の特異な生徒は漢字のイメージ、姿がはっきりと記憶されているだけなのです。
2.初見文章読解問題・・・4択問題の解答法については前述しましたが、ここでは短期間で身につく「読解問題解答力」について述べてみます。楽しみで行う読書との大きな違いは、読解問題本文には必ず後ろに「答えなければならない問題」が付いているということです。つまりメインは文章ではなく「問題・設問」の方である。こういう問題が出される、この手の問題が作られる・・・といった問題作成のパターン、裏側を知ることが大切なのである。
その考えを踏まえての具体的な対策としては、自分で解答することなく、問題と解答を照らし合わせてひたすら見るのである。2,3冊の問題集で行えば、丸がもらえる、点が取れる解答というのがおのずと見えてきます。
国語は文章作成者というより問題作成者との戦いです。ひっかけの感じや、落とし穴の手口をつかむ必要があるのです。そして実際に解答する際は、文章作成者、いわゆる作家があなたの味方です。あなたは作家と協力して、題作成者と戦う…これが国語文章読解なのです。私は以前、小学4年生~中学3年生の生徒を一緒にして文章読解教室を開いていたことがありますが、問読解問題解答方法をマスターした生徒なら小4でも中3に負けないということを知りました。同じ教室にいる5つ違いのお兄さんに負けていない小学生を多く目にしました。(ほかの科目ではこんなことはあり得ませんが・・・)
入試の国語はどの生徒にとっても初見の文章であるということと、他の科目は入試勉強してくるものは多いが、国語はほとんどノータッチの生徒が多いということを考え合わせると、読解問題解答力は極めて有利な武器となりえます。早ければ1カ月で身につく武器です。ぜひ頑張っていきましょう。